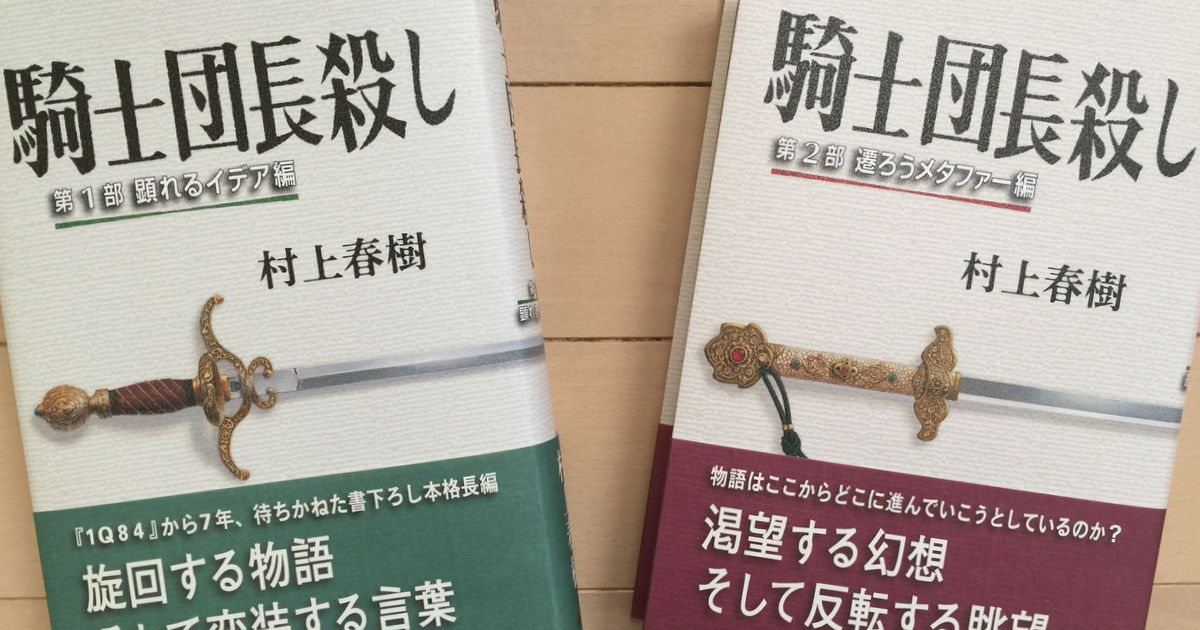
村上春樹の新作「騎士団長殺し」を読みました。長編小説としては「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」以来4年ぶりでしたが、個人的には原点に立ち返ったようなスタイルが読みやすくボリュームも十分。
淡々とした日常の中にも『死』の意味合いを描くことに苦心した跡が伺えますが、いつにも増して希望の感じられる読後感が印象的。最後まで読み終えて、主人公たちの前途を祈らずにはいられない気持ちになりました。
谷の向こうの隣人からの奇妙な依頼
<あらすじ>
妻に突然離婚を切り出され、傷心の果てに山の上の小さな家で暮らすことになった肖像画家の「私」。その家の元の住人である画家・雨田具彦が描き残した「騎士団長殺し」という一枚の絵を発見したことから、次々と不思議な出来事に巻き込まれていく・・。
それまで肖像画家として生計を立てていた主人公が、小田原の山中にある小さな邸宅で、創作活動に打ち込む、という世捨て人のような生活を始めるところから物語は始まります。
テレビもインターネットもない環境で、LPでクラシック音楽を聴きながら日々の創作に向き合う姿は、とても現代人のライフスタイルとは思えず、ある意味で羨ましくもあるのですが、そんな静かな暮らしに一人の闖入者が訪れます。
ある日突然、主人公に肖像画の依頼をしてきた、谷の向かいの邸宅に住む「免色」という男。謎に包まれたこの男の出現により、主人公の人生が思わぬ方向へ進むことになるのですが、彼の真の目的は肖像画を描いてもらうことだけではありませんでした。
山の上の邸宅という、物理的に隔離された空間の中で繰り広げられる、謎が謎を呼ぶ展開はミステリ仕立てのようでもあり、ついつい続きが気になってしまう中毒性があります。思えば、村上春樹の作品でも、ここまで舞台が限定された作品はあまりなかったのではないでしょうか?
3.11から6年後に書かれた鎮魂のための物語
「騎士団長殺し」は、モーツァルトのオペラ『ドン・ジョバンニ』を題材に描かれた日本画ということで、画面の中で騎士団長と呼ばれる男が血を流しながら剣で刺されている、かなり鮮烈なイメージが文章からも伝わってきます。
不思議な魅力を持ったこの作品は、作者の雨田具彦がウィーン留学時代に目にしたヒトラーによる粛清や、その弟が徴兵先で関わったとされる南京事件の影響を受けているらしく、犠牲になった多くの人々の『死』を想起させるものとなっています。
さらに、この小説のラストでは、物語の数年後に東日本大震災が起こり、震災から少し前の2000年代初頭が舞台だったことが明らかになるのですが、そのような時代設定からも「騎士団長殺し」が3.11を強く意識した作品だということが分かるでしょう。
『殺し』というキーワードからは、ネガティブで怖い印象を抱く人も多いかもしれませんが、作中に出てくる「騎士団長殺し」が鎮魂のために描かれた作品だったのと同じように、本作は東日本大震災の犠牲者の魂を鎮魂するために書かれた側面が大きいと思うのです。
個性的なキャラクターが織り成す普通ではない日常
3.11がテーマになっていると言うと、重々しい雰囲気に感じられるかもしれませんが、そんなことばかりではなくて、個性的なキャラクターが織り成す、ちょっと愉快な群像劇という側面も併せ持ちます。
とりわけチャーミングで愛らしいのが、絵からそのまま飛び出してきたような小さな『騎士団長』でしょう。これは実際に雨田具彦の絵画から出てきたのではなく、なんとイデア(=理念または観念)が絵のモチーフを借りて具現化した姿なのだとか・・。
村上春樹の作品には、ちょっと不可思議な存在が登場するのがおなじみですが、まさか『イデア』や『メタファー』といった概念そのものが登場人物になるとは思わなかったので、これにはかなり意表を突かれました。「顕れるイデア」「遷ろうメタファー」というサブタイトルの意味はここにあったんですね。。
騎士団長は主人公に助言を与えてくれる頼もしい存在ですが、それに対してどこか油断できないのが、奇妙な隣人・免色渉です。彼も村上作品によく出てくる「不思議な人物」の典型ではありますが、主人公を凌駕してしまうほどの存在感を持っているだけに、本作のもう一人の主役と言ってもいいかもしれません。
私が一番お気に入りなのは、主人公の絵のモデルをやることになった13歳の少女・秋川まりえです。無口で普段はほとんどしゃべらないけど、優れた直感力と強い意志を秘めた、不思議な魅力を持った女の子・・。
物語の後半では、そんな彼女の冒険譚が一つのクライマックスとなっているだけに、誰しもハラハラと感情移入しながら楽しめるのではないでしょうか?
「騎士団長殺し」に見る異常な懐古趣味
そんな風に、村上春樹ならではのテーマに正面から取り組んだ本格長編ですが、私が読んでいて一番気になったのは、執拗なまでの古いテクノロジーへのこだわりです。
山の上の一軒家という辺鄙な場所に住んでいることもあるのですが、主人公の下を訪れる登場人物たちが運転する自動車が、まるで一台一台人格を持っているかのように、個性豊かに描かれています。
また、家の前の持ち主・雨田具彦はLP盤レコードの愛好家でしたが、その息子の雨田政彦はカセットテープを未だに愛用していたりと、徹底したレトロ懐古主義が垣間見れます。何しろ21世紀に入ってるというのに、主人公は携帯電話すら持っていないのですから・・。
私にはまるで「テレビや電話といったテクノロジーがどんどん古い時代へ逆行してしまう」時間退行現象を描いたフィリップ・K・ディックのSF小説「ユービック」を彷彿させるのですが、そんなモチーフに込めた作者の意図は何だったのでしょうか?
免色がインターネットを駆使したビジネスを手掛けていたり、雨田政彦がMacを使ったデザインを生業にしている一方で、携帯電話を使わない(使えない)主人公や秋川まりえが、物語で重要な役割を演じることになるのは、決して偶然ではないでしょう。
決定的な破壊や殺戮を前にした時、人はどこまでも無力でしかあり得ないのだから、そんな時に頼れるのは実際に手に触れることのできる『ぬくもり』や記憶なのだ。そんな言葉にならないメッセージを、この作品から強く感じました。
